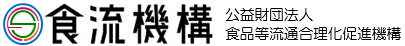食料システム法について
Ⅰ.目的
食品等事業者が食料システムにおいて農林漁業者と一般消費者をつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化をもって、農林漁業及び食品産業の成⾧発展並びに一般消費者の利益の増進に資する。
Ⅱ.法律の概要
1.題名
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)
2.食品等持続的供給基本方針の策定
農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、次の事項を内容とする食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(食品等持続的供給基本方針)を定める。
- ①安定取引関係確立事業活動等の促進に関する事項
- ②連携支援事業の促進に関する事項
- ③安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関するその他重要事項
3.食品等の持続的な供給の実現に向けた事業活動の促進
(1)食品等事業者が、次の事業活動に関する計画を作成
- ①安定取引関係確⽴事業活動(農林⽔産業と食品産業の連携強化)
- ②流通合理化事業活動(食品等の流通の効率化、付加価値向上等)
- ③環境負荷低減事業活動(温室効果ガスの排出量の削減等)
- ④消費者選択⽀援事業活動(持続可能性に配慮した物の選択を消費者が行うことに寄与する情報の伝達等)
※ ①~④には技術開発利⽤、事業再編を含む。
(2)地方公共団体、一般社団法⼈等、①の事業活動を連携して支援しようとする者は、連携支援計画を作成
(3) 農林水産大臣が(1)又は(2)の計画を認定した場合、支援措置を実施
- ①食品等持続的供給推進機構(食料システム機構)による債務保証
- ②日本政策金融公庫による⾧期低利融資
- ③農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備の供用
※このほか、税法にて、中小企業経営強化税制、カーボンニュートラル投資促進税制等の税制特例
(4)食品等持続的供給推進機構の指定
農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的し、次の業務を適正かつ確実に行うことができる法人を、食品等持続的供給推進機構として指定する(令和7年10月1日指定)。
- ①認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務保証。
- ②認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対する必要な資金のあっせん。
- ③食品等の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究及びその成果を普及すること。
- ④食品等の持続的な供給に関する照会・相談への対応
4.食品等の取引の適正化
(1)農林水産大臣が、食品等取引実態調査を実施。
(2)飲食料品等事業者・農林漁業者は、次の措置を講ずるよう努力。
- ①持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して協議の申出がされた場合、誠実に協議。
- ②持続的な供給に資する取組(商慣習の見直し等)の提案があった場合、検討・協力。
(3)農林水産大臣が、事業者の行動規範(判断基準)を策定。
(4)農林水産大臣は、次の措置を実施。
- ①適確な実施を確保するため必要な場合、指導・助言を実施。
- ②実施状況が著しく不十分な場合、勧告・公表を実施。(勧告の実施に必要な場合、報告徴収・立入検査を実施。)
※不公正な取引方法に該当する事実がある場合、公取委に通知。
(5)農林水産大臣が、取引において、通常、費用を認識しにくい飲食料品等を指定。その費用の指標の作成・公表等を行う団体を認定